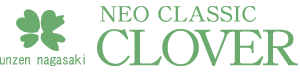仏事
亡き方を偲ぶお手伝いをお菓子は担っています
仏教では、初七日や四十九日、一周忌・三回忌などの法要や法事の際に、参列者の方々への引き出物としてお菓子を用意することがあります。
こうしたお菓子は「引き菓子」とも呼ばれ、参列者が法事から帰った後、故人を偲びながらお茶と共にいただいてほしいという喪主の願いが込められています。
この場合の「引き菓子」は、日持ちのするものを選び、小分けができる個包装のものが最適です。
また法事の際に仏壇の前には「御供物(おくもつ)」をお供えします。お供え物としては、飲食物として「仏飯」「お餅」「お菓子」「果物」などを用意します。
一般的に「仏飯」や「お餅」などは遺族が用意しますが、「お菓子」や「果物」などは、故人への捧げものとして、法事の参列者が持参する場合もあります。
お供え物に用いるお菓子は、法事の後で参列者や親族で分け合うこともありますので、焼き菓子など、日持ちがするものを選ぶのが基本です。
こうしたお菓子は「引き菓子」とも呼ばれ、参列者が法事から帰った後、故人を偲びながらお茶と共にいただいてほしいという喪主の願いが込められています。
この場合の「引き菓子」は、日持ちのするものを選び、小分けができる個包装のものが最適です。
また法事の際に仏壇の前には「御供物(おくもつ)」をお供えします。お供え物としては、飲食物として「仏飯」「お餅」「お菓子」「果物」などを用意します。
一般的に「仏飯」や「お餅」などは遺族が用意しますが、「お菓子」や「果物」などは、故人への捧げものとして、法事の参列者が持参する場合もあります。
お供え物に用いるお菓子は、法事の後で参列者や親族で分け合うこともありますので、焼き菓子など、日持ちがするものを選ぶのが基本です。